『
真理はたいまつである。しかも巨大なたいまつである。 だから私たちはみんな目を細めてそのそばを通りすぎようとするのだ。 やけどする事を恐れて。』
-
※
(その他)
花を与えるのは自然であり、それを編んで花輪にするのが芸術である。
青年は教えられることより刺激されることを欲するものである。
馬で行くことも、車で行くことも、 二人で行くことも、三人で行くこともできる。 だが、最後の一歩は自分ひとりで歩かなければならない。
人生は全て次の二つから成り立っている。 したいけど、できない。できるけど、したくない。
人生で一番楽しい瞬間は、誰にも分からない二人だけの言葉で、 誰にも分からない二人だけの秘密や楽しみを、ともに語り合っている時である。
誰一人知る人もない人ごみの中をかき分けていくときほど、 強く孤独を感じるときはない。
あの人が私を愛してから、 自分が自分にとってどれほど価値のあるものになったことだろう。
二十代の恋は幻想である。 三十代の恋は浮気である。 人は四十代に達して、 初めて真のプラトニックな恋愛を知る。
涙とともにパンを食べたものでなければ人生の味はわからない。
楽しく生きていきたいなら、 与えるための袋と、受け取るために袋を持って行け。
時を短くするものはなにか――活動。
時を絶えがたくするものはなにか――怠惰。
僕はどうやらこの世における一個の旅人に過ぎないようだ。 君たちとてそれ以上のものだろうか?
10歳にして菓子に動かされ、20歳にしては恋人に、30歳にして快楽に、 40歳にしては野心に、50歳にしては貪欲に動かされる。 いつになったら人間はただ知性のみを追って進むようになるのであろうか。
王様であろうと百姓であろうと、 自分の家庭で平和を見出す者が一番幸福な人間である。
喜んで行ない、そして行ったことを喜べる人は幸福である。
自分自身の道を迷って歩いている子供や青年の方が、 他人の道を間違いなく歩いている人々よりも好ましく思う。
財布が軽ければ心は重い。
誠実に君の時間を利用せよ! 何かを理解しようと思ったら、遠くを探すな。
真理はたいまつである。しかも巨大なたいまつである。 だから私たちはみんな目を細めてそのそばを通りすぎようとするのだ。 やけどする事を恐れて。
墓の下に眠っている人々を羨まなければならないとは、何という情けない時代だろう。
私が過つと誰でも気づく。私が嘘をつくと誰も気付かない。
立法者にしろ革命家にしろ、平等と自由とを同時に約束する者は、 空想家か、さもなくば山師だ。
なぜいつも遠くへばかりいこうとするのか? 見よ、よきものは身近にあるのを。ただ幸福のつかみかたを学べばよいのだ。 幸福はいつも目の前にあるのだ。
決然たる意志の持ち主は、世界を自分に合わせて形作る。
人々が自分に調和してくれるように望むのは非常に愚かだ。
※











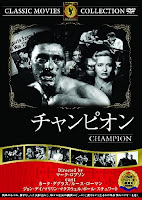









.jpg)








.jpeg)
%20-%20%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC.gif)






.jpg)

.jpg)










_-_n._23185_-_Socrate_(Collezione_Farnese)_-_Museo_Nazionale_di_Napoli.jpg)











